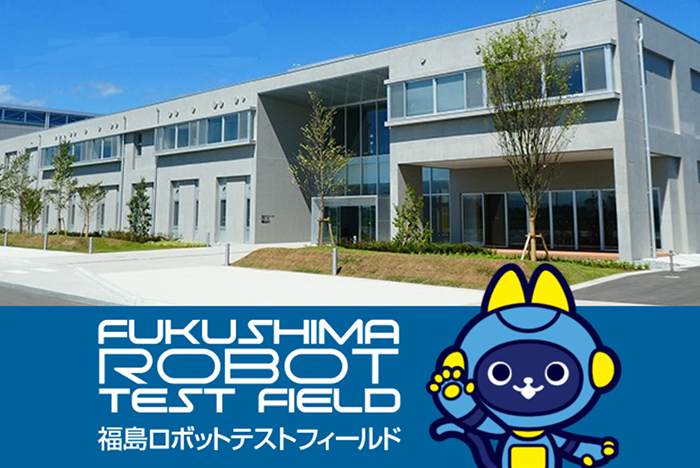【活動報告】令和7年度「復興知」事業 成果報告会を開催しました
- 大学研究等
- 事業レポート
令和7年9月5日(金)に、「令和7年度『復興知』事業 成果報告会」を開催しました。
福島県浜通り地域等では、東日本大震災以降、全国から多くの大学等が、それぞれに有する知見を生かして地域に寄り添いながら復興支援活動を行っており、本県の復興に資する「知」が蓄積されています。
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構では、これらの大学等の知見を生かし、浜通り地域等に人材育成基盤を構築するため、2021年度から「大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業(「復興知」事業)」を5ヵ年の事業として実施しています。採択された21のプログラムにおいては、放射線・リスコミ、農業、ロボット・ドローン、エネルギー等の様々な分野で教育研究活動が行われており、今年度が最終年度となります。
今年度は、5年間の事業を通した取組や成果を学生が中心となって発表し、参加者と交流することによって自身の学びをさらに深めることを狙いに、「成果報告会」として開催いたします。また、大学間の交流が浜通りにおける今後の教育研究・人材育成の更なる発展や新たな展開等につながる連携のきっかけとなることを目指すとともに、「復興知」事業の取組と成果を広く皆様に知っていただくことを目的として、本報告会を開催しました。
また、9月6日(土)に実施した学生ワークショップでは、当事業に参加してきた学生たちが、「復興知」事業で経験したこと」等をテーマに語り合いました。
開催内容は以下の通りです。
1 開催日時・場所
日時:令和7年9月5日(金) 12:45 ~ 17:00(開場 12:15)
9月6日(土) 9:30 ~ 12:00(開場 9:00)
会場:9月5日(金) CREVAおおくま
(福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野116-5)9月6日(土) 大熊町連携大学等研究・支援センター内大阪大学福島拠点
(福島県双葉郡大熊町大字下野上字清水309番地)2 開催方法
現地開催のみ
3 内容
令和7年度「復興知」事業 成果報告会 プログラム[PDF/108KB]
4 当日の様子
〇 令和7年度 成果報告会
動画(学生による取組発表 会議室1A) / 動画(学生による取組発表 会議室1B)
( 福島イノベ機構公式youtube @fukushimainnov )
〇 ポスター
現地会場で展示した採択全21事業のポスターは、以下のとおりです。
①会津大学(南相馬市)【R7成果報告会ポスター(1,196KB)】
②大阪大学(飯舘村ほか)【R7成果報告会ポスター(1,715KB)】
③東京農工大学(富岡町)【R7成果報告会ポスター(810KB)】
④獨協大学(田村市)【R7成果報告会ポスター(1,504KB)】
⑤近畿大学(川俣町)【R7成果報告会ポスター(440KB)】
⑥日本大学(葛尾村ほか)【R7成果報告会ポスター(1,521KB)】
⑦東京大学(飯舘村)【R7成果報告会ポスター(985KB)】
⑧長崎大学(川内村ほか)【R7成果報告会ポスター(1,077KB)】
⑨東京大学(新地町)【R7成果報告会ポスター(391KB)】
➉郡山女子大学(葛尾村)【R7成果報告会ポスター(2,466KB)】
⑪東北大学(南相馬市ほか)【R7成果報告会ポスター(443KB)】
⑫福島工業高等専門学校(広野町)【R7成果報告会ポスター(572KB)】
⑬東京農業大学(相馬市)【R7成果報告会ポスター(817KB)】
⑭早稲田大学(広野町ほか)【R7成果報告会ポスター(558KB)】
⑮弘前大学(浪江町)【R7成果報告会ポスター(1,354KB)】
⑯福島大学(南相馬市ほか)【R7成果報告会ポスター(842KB)】
⑰東京大学(いわき市)【R7成果報告会ポスター(1,641KB)】
⑱東京大学(楢葉町ほか)【R7成果報告会ポスター(914KB)】
⑲立命館大学(双葉町ほか)【R7成果報告会ポスター(958KB)】
⑳東京農業大学(浪江町ほか)【R7成果報告会ポスター(2,211KB)】
㉑慶應義塾大学(田村市)【R7成果報告会ポスター(246KB)】
〇 学生ワークショップ
大阪大学福島拠点を会場に、採択校より70名の学生が参加し、『「復興知」を語ろう~交わる想い、広がる未来~』と題したワークショップを開催。
大阪大学中島特任教授の司会のもと、13グループに分かれて、以下の4テーマについてディスカッションを行いました。
【テーマ】
①「復興知」事業で経験したこと
②「復興知」事業に関る前と後で、自分の考え方や行動がどう変化したか
③「復興知」事業を通して感じた福島に必要なもの、こと
④大学等を卒業した後の自分が、福島とどのような関り方ができるか



各グループでは、採択校の先生方1名がファシリテーターとしてサポート役を担い、
ワークショップ終盤には各グループの代表者が「会場全体へ共有したいこと」を発表しました。



お問い合わせ先
教育・人材育成部 教育研究支援課
TEL:024-581-6891